【2022 最新版】第1回 金沢市統一テスト「 理科 」の傾向と対策
第1回金沢市統一テスト「理科」の出題傾向と対策法をご紹介していきます。
ザワナビでは高校受験に役立つ情報をLINEで随時配信中!! LINE限定の情報や学習アドバイスもあるので、ぜひお友達登録お願いします!!
理科は「物理分野」「化学分野」「生物分野」「地学分野」の4分野から出題されますので、分野ごとに出題内容を整理していきます。それに加えて、金沢市統一テストの理科の[1]の問題は、数学の[1]と同様、比較的難易度の低い問題をいろいろな単元からピックアップして出題する小問集合的なものとなっています。この[1]は通常と切り離して取り扱おうと思いますので、先の4分野+[1]の問題の出題内容を整理し、その対策法をご紹介していきます。
[1]の問題の出題内容
まず[1]の出題内容を整理していきます。前述の通り比較的難易度が低い問題をいろいろな分野からセレクトして出題してくるのが[1]の問題の特徴です。
| 年度 | 出題内容 |
| R3 | 背骨のある動物・背骨のない動物と動物の分類、大気の動き、プラスチックの種類と性質、仕事(動滑車と定滑車) |
| R2 | 植物の世界(蒸散量)、大地の変化(花こう岩)、身の回りの物質(気体の発生)、運動とエネルギー(斜面上の物体の運動) |
| R1 | 大地の変化(地震)、化学変化とイオン(塩化銅水溶液の電気分解)、電気の世界(電磁誘導)、生命の連続性(精細胞) |
| H30 | 生命の連続性(遺伝の規則性と遺伝子)、大地の変化(火山と噴出物)、化学変化とイオン(木炭電池) |
| H29 | 大地の変化(地震)、身の回りの物質(気体の性質)、身の回りの現象(音の世界) |
| H28 | 身の回りの物質(物体と物質)、身の回りの現象(音の世界など) |
| H27 | 身の回りの物質(気体の性質)、動物の生活と生物の変遷(筋肉、ムセキツイ動物)、電気の世界(電磁誘導など) |
| H26 | 電気の世界(回路と電流電圧・オームの法則)、化学変化とイオン(酸とアルカリ)、動物の生活と生物の変遷(血管) |
過去8年間の出題内容をまとめるとこのようになります。
比較的よく出題される単元とそうでない単元がこの表から見てとれますが、どの単元から出題されるかは実際の出題を見てみなければ分かりません。
前年と同じ単元からの出題はそう多くないと思われます。
難易度は比較的基礎的な問題が多くなっており、学校のワーク等で基礎問題をしっかりとやりこむことで十分に正解できる問題とも言えます。
基礎的なレベルですから、理科が得意な方は完答を目指して、理科が苦手な方は、これ以降さらに難しくなるので、出来るだけ[1]で得点を稼ごうという視点が大切です。
特に理科が苦手な方は、こういった小問集合の問題を探して毎日にように問題に取り組むと良いでしょう。
物理分野からの出題傾向
ここからは理科の4分野ごとの出題内容を整理していきます。まずは物理分野。
物理分野を苦手とする人は少なくありません。まずはどういった単元が狙われることが多いのかをしっかりと把握しておきましょう。
| 年度 | 出題内容 |
| R3 | 運動とエネルギー(中3):物体の運動 身のまわりの現象(中1):音 |
| R2 | 身のまわりの現象(中1):凸レンズの像 電気の世界(中2):抵抗、電圧・電流のグラフ(生物の体のつくりとはたらき「反射」との融合問題) |
| R1 | 運動とエネルギー(中3):斜面上の物体の運動(重力の向き、垂直抗力の向き、瞬間の速さ、台車の速さ) |
| H30 | 電気の世界(中2):オームの法則、直列回路電流、電圧、抵抗、電熱線・電力量、電気用図記号
運動とエネルギー(中3):力が働く物体の運動、働かない物体の運動、記録テープ・台車 |
| H29 | 電気の世界(中2):静電気と電流、真空放電、電子、静電気
身のまわりの現象(中1):光の屈折、反射 |
| H28 | 身のまわりの現象(中1):圧力・浮力
運動とエネルギー(中3):等速直線運動、慣性の法則 |
| H27 | 身のまわりの現象(中1):力とそのあらわし方、バネの伸びと力の大きさの関係
電気の世界(中2):電流と磁界 |
| H26 | 身のまわりの現象(中1):圧力、フックの法則、浮力、計算問題
運動とエネルギー(中3):力が働く物体の運動、摩擦力、垂直抗力、分力の作図 |
第1回金沢市統一テストの試験範囲となっている物理分野から、特にこれといった傾向もなく満遍なく出題されています。
過去8年間で、
中1 身のまわりの現象 6回 (圧力・力・浮力 3回、光 2回、音 1回)
中2 電気の世界 4回
中3 運動とエネルギー 5回
出題されており、中1の身のまわりの現象からの出題が若干多いかなといったところですが、ほぼ誤差の範囲です。
中1の身のまわりの現象からの出題では、力や光からの出題多く、音からの出題はありません([1]で出題されたことはある)
中3の運動とエネルギーからの出題は、例年似たような問題となっており対策はしやすいかなと思います。
中2はとにかく電気の世界をしっかりと学習するし、どこを突かれても大丈夫なようにしておくことが理想です。
化学分野からの出題傾向
続いて化学分野。
化学分野もまずは過去の出題内容を整理し、どういった単元が狙われているのかを整理しましょう。
| 年度 | 出題内容 |
| R3 | 化学変化とイオン(中3): 電気分解 |
| R2 | 化学変化とイオン(中3):中和、発熱反応 |
| R1 | 化学変化と原子・分子(中2):酸化と還元(石灰石、化学反応式、モデル、酸化銅における銅の質量と酸素の質量の関係) |
| H30 | 身のまわりの物質(中1):プラスチック、密度、有機物
化学変化と原子・分子(中2):銅の酸化、化学変化の原子モデル、銅と酸素の化合比など計算問題 |
| H29 | 身のまわりの物質(中1):溶解度と再結晶
化学変化とイオン(中3):化学変化と電池、中和反応、イオン式 |
| H28 | 化学変化と原子・分子(中2):鉄と硫黄の化合
化学変化とイオン(中3):中和反応 |
| H27 | 化学変化とイオン(中3):中和反応(一部中2の化学反応式についての出題あり)
化学変化と原子・分子(中2):熱分解、水上置換法、化学式 |
| H26 | 身のまわりの物質(中1):物体と物質、メスシリンダー、上皿てんびんの操作、密度
化学変化と原子・分子(中2):酸化銅の還元、化学反応式、計算問題 |
中2内容の「化学変化と原子・分子」は特に頻出単元となっています。基礎的な化学反応式や酸化・分解などの基礎内容、さらにそれにまつわる実験の注意点を聞く問題から、計算問題まで出題されています。
また中3内容の「化学変化とイオン」も頻出ですのでよく確認しておくと良いでしょう。
自分の苦手がどの部分かにはよりますが、まずは暗記で対応できる部分でしっかりと点数を取れるようにしていきましょう。その上で計算問題に対応力強化を図ってください。
理科の計算問題だけの問題集なども発売されていますので、そういった問題で集中的に練習するのも良いでしょいう。
中3内容の「化学変化とイオン」からの出題は比較的対策がしやすいように思います。というのもだいたい出題されている内容は「中和」絡みの問題が多く、まずはその部分を中心に学習をしていけば良いと思います、もちろん中2の「化学変化と原子・分子」同様、暗記事項でしっかりと点数を取れるようにしていくことが重要です。
理科に限ったことではありませんが、よく「記述が多い」ということが指摘されていますが、上位校狙いでなければ、記述以外の部分でしっかりと加点していけば、たいていの高校の合格ラインは見えてきます。さらに上位校狙いであっても、まずこの記述以外でしっかりと点が取れなければ話になりませんし、記述記述と言っても、どこかの問題集で見たことのある記述問題も多く、全く未知のレベルの記述はそこまで多くありません。
なお化学分野からはその他中1「身のまわりの物質」からも出題されます。キーワードは「密度」と「溶解度と再結晶」。それぞれの典型問題に多く触れておきましょう。
(参考:単元ごとの出題回数)
中1 身の回りの物質 3回
中2 化学変化と原子・分子 5回
中3 化学変化とイオン 5回
生物分野からの出題傾向
理科の「生物分野」からの出題もまずは整理しておきましょう。
| 年度 | 出題内容 |
| R3 | 植物の働き(根・茎・葉) |
| R2 | 植物の世界(中1)+生命の連続性(中3):離弁花類、胚珠、細胞分裂、卵細胞、精細胞、胚の数 |
| R1 | 生物の体のつくりとはたらき(中2):消化と吸収(ペプシン・ブドウ糖、消化液、柔毛のはたらき) 植物の世界(中1)+動物の生活と生物の変遷(中2):光合成と呼吸、肺による呼吸 |
| H30 | 植物の世界(中1):顕微鏡の使い方、ゾウリムシ、顕微鏡の倍率、多細胞生物
生命の連続性(中3):生物の成長と生殖、細胞分裂の順 |
| H29 | 植物の世界(中1):植物の分類、被子植物、離弁花・合弁花、胞子
動物の生活と生物の変遷(中2):血液の循環 |
| H28 | 動物の生活と生物の変遷(中2):セキツイ動物、両生類、相同器官
生命の連続性(中3):脂肪、受粉、クローン、デオキシリボ核酸(一部中1内容も含まれる) |
| H27 | 植物の世界(中1):光合成、対照実験、光合成の原料
生命の連続性(中3):花粉管、被子植物の受精、栄養生殖 |
| H26 | 植物の世界(中1):蒸散
生命の連続性(中3):メンデル、分離の法則、優性形質・劣性形質 |
過去8年間の単元ごとの出題回数をまとめると以下のようになります。
中1 植物の世界 7回
中2 動物の生活と生物の変遷 4回
中3 生命の連続性 5回
中1「植物の世界」>中3「生命の連続性」>中2「動物の生活と生物の変遷」の順でよく出題されていることがわかります。
対策についてもこの順番で行うと良いでしょう。
中1「植物の世界」からは蒸散や光合成、植物の分類など、色々な問題が出題されていますので、幅広い対策が求められます。
一方で中3「生命の連続性」は単元の特性上、「遺伝」に関する部分がやはりよく聞かれます。覚えるべき内容は中1「植物の世界」よりも少ないですから、この「生命の連続性」をまずはしっかりと仕上げていくと良いでしょう。
中2「動物の生活と生物の変遷」も中1「植物の世界」同様、幅広い対策が求められます。
例えば学校の定期テストなどでこれらの単元の復習をしてみるのも良いかもしれません。
地学分野からの出題傾向
最後に「地学分野」です。
中3で学習する「地学」については、まだ未習ということもあり、出題されるのは中1「大地の変化」か中2「天気とその変化」か、もしくはその両方からとなります。
実際の出題内容を整理してみましょう。
| 年度 | 出題内容 |
| R3 | 天気とその変化(中2):雲のでき方 大地の変化(中1):マグマ、火成岩 |
| R2 | 天気とその変化(中2):偏西風、移動性高気圧、天気の特徴、梅雨前線、小笠原気団 |
| R1 | 天気とその変化(中2):乾湿計、気圧、天気図、水蒸気量、湿度の変化 |
| H30 | 天気とその変化(中2):天気記号、雲量、低気圧の風の向き、前線とそのまわりの天気の変化 |
| H29 | 天気とその変化(中2):天気図の読み取り、前線、気団 |
| H28 | 大地の変化(中1):火山と噴出物、斑状組織、凝灰岩 |
| H27 | 大地の変化(中1):地震、初期微動継続時間、P波・S波、計算問題
天気とその変化(中2):天気記号、天気図の読み取り、前線、高気圧、気圧と時刻の関係 |
| H26 | 大地の変化(中1):火成岩、等粒状組織、花こう岩、流紋岩
天気とその変化(中2):前線、天気図の読み取り、梅雨前線、小笠原気団 |
平成28年度以降は「地学分野」からの出題は大問1つとなっています。
過去8年間分の出題回数を単元ごとにまとめると
中1 大地の変化 4回
中2 天気とその変化 7回
となっており、圧倒的に「天気とその変化」がまずは大事であるということがお分かりいただけるのではないかと思います。
「天気とその変化」からは天気図の読み取り、あとは前線関係の問題(例えば前線が通過した後の天気の変化などの典型問題)、気団に関する問題などが出題されています。標準的な問題ですので学校のワークや市販の問題集でしっかりと練習しておけば十分対応可能です。
「大地の変化」はここ4年間出題されていませんが、過去は「火山と噴出物」「地震」から出題されており、まずはこれらをしっかりと復習しておくことが期待されます。
目標点別 第1回 金沢市統一テスト 理科 攻略法
ここまでで金沢市統一テストの理科でどのような問題が出題されているかをご紹介してきました。
ではこの金沢市統一テスト対策をどのように進めていけば良いのか。
これは普段数学の点数がどれだけ取れているかにより対策の仕方は変わってくるため、理想的なのは塾の先生に個別アドバイスをもらうことですが、ここでは目標点別に対策の参考となる方法をご紹介しようと思います。
0点〜平均点を目指す
基礎的なレベルの知識事項がしっかりと身についていない可能性がありますので、まずは知識をしっかりとインプットしていくことに重点を置きます。
用意するテキストとしては
まずは「中1理科をひとつひとつわかりやすく」「中2理科をひとつひとつわかりやすく」「中3理科をひとつひとつわかりやすく」のわかりやすく系のテキストをインプット教材として利用します。
演習用教材としては、
「受験生の50%以上が解ける 落とせない入試問題 理科 改訂版」を使用します。
受験生の50%以上が解ける シリーズは問題数も少ないので、全体的な復習をサクッとしてしまうにはうってつけです。
平均点〜80点
平均点から80点ぐらいまでの点数を目標にする方でも知識事項に不安がある場合は、0点〜平均点を目指すで紹介した教材を利用するか、学校のワークを総復習すると良いでしょう。
そのうえで取り組むべきはこちらの教材。
この問題集は標準的なレベルの問題にどう取り組むのか、その「解き方」を身につけることをコンセプトにしたテキスト。
典型的な問題の解き方をここでインプットします。
そのうえで、
「2021 2022年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 652題 理科 化学・物理・生物・地学」
分野別過去問に取り組み、演習量を確保していきましょう。
80点以上
80点以上を目指す上位校志望者の方も、基本的には分野別過去問だけで十分力がつくと思いますが、全国高校入試問題正解からよく出る問題をピックアップして、追加で演習することで確実に80点以上を狙うことができます。
今回ご紹介した内容を踏まえて、金沢市統一テストの対策を万全なものにしてください。
学習サークル ザワナビ で金沢市統一テスト対策をする
ザワナビプロデュースで運営されている学習サークル ザワナビで金沢市統一テスト対策を集中的に行うことも可能です。教室に通うコースだけでなくWEBコースもあるので、通室せずに受験のプロのサポートのもと、金沢市統一テスト対策を進めることも可能です。














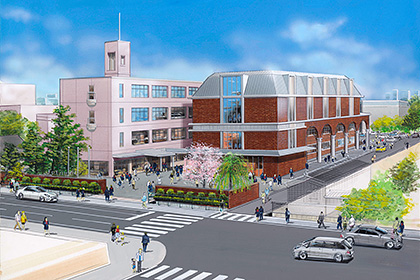
Comment
国語もお願いします!!!